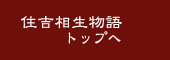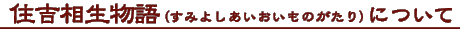
【書誌】
五巻五冊。表紙寸法、縦26.2糎、横18.5糎。袋綴。
巻一24丁、巻二18丁、巻三18丁、巻四15丁、巻五11丁、著者は一無軒道冶(いちむけんどうや)。刊記は河勝又兵衛、その右に刊行年月が掘られていたはずが、削り取られている。袋綴、紺色表紙。
成立は延宝六(1679)年とされる。
【内容】
摂州住吉神社境内および付近の名所を記載したもので、地誌として分類されてきた。挿絵は豊富で28丁に及ぶ。神社録・旧跡・和歌・遷宮・神宝・年中祭祀・神宮寺草創などの項目のもと、住吉大社の地理的説明に留まらず、その内容は古代の神話・伝説・説話へと広がってゆく。一例を挙げると謡曲『海士』の世界も表現されている。―― 藤原不比等の子房前が、志度の浦の房前で亡くなった母の追善のために志度の浦へ赴く。そこで出会った海人が、面向不背の珠を龍神に取られたこと、それを取り返すために不比等(淡海公)が身をやつしてこの志度の浦に下り、海人と契りを結びひとりの子を儲けたこと、その子が房前の大臣であることなどを語る。海人は、珠を取って帰ってきたならばこの子を藤原家の後継ぎにしようという淡海公の言葉を得て、海人は海底の竜宮城に行って玉を取り返すが、龍神の追跡を受ける。海人は剣で乳の下を切り、玉を押し込め、縄を引き上げさせるが、死の息の下で海人は乳の下を見よと言って玉の存在を伝え、房前の大臣は藤原家の後継ぎになったのだと海人は語る。そして自分こそがその海人の亡霊(つまり房前の母)であると名乗った後、弔いを頼んで姿を消す。十三年忌の供養を行う房前の前に亡霊は龍女の姿で現われて、経文のありがたさを喜び舞を舞う。「法華経」の功徳で龍女は成仏し、志度寺は仏教の霊地となった。―― 『住吉相生物語』は海人の珠取りをもっぱらとするダイジェストであるが、見開き二面の挿絵が描かれている。